2025.09.26
【2025年版】埼玉の窓の結露対策|カビ・寒さ・光熱費の悩みを根本解決!
埼玉県にお住まいで、冬の窓の結露に悩んでいませんか。
毎朝、窓ガラスやサッシにびっしりと付いた水滴を拭き取る作業は、時間も手間もかかり本当に大変です。
放置すればカビが発生し、家族の健康が心配になることもあるでしょう。
さらに、窓からの冷気で部屋がなかなか暖まらず、暖房費がかさんでしまうのも大きな悩みです。
この記事では、そんな埼玉の冬の悩みを根本から解決するための結露対策を網羅的に解説します。
手軽に始められるDIYから、専門家による本格的なリフォーム、などあなたの家に合った最適な方法がきっと見つかります。
面倒な結露掃除から解放され、暖かく快適な冬を過ごすための第一歩を、ここから踏み出しましょう。
そもそも、なぜ窓に結露が?埼玉の気候と放置する3つのリスク

結露は、室内の暖かく湿った空気が、外気で冷やされた窓ガラスやサッシに触れることで発生します。
空気は温度が高いほど多くの水蒸気を含むことができますが、冷たいものに触れて温度が下がると、含みきれなくなった水蒸気が水滴に変わるのです。
これが結露の正体です。
特に冬の埼玉県では、晴れた日の放射冷却で朝晩は強く冷え込む一方、日中は日差しで室内が暖められます。
この大きな寒暖差が、窓の内外で著しい温度差を生み、結露を発生させやすい環境を作っています。
この厄介な結露を「ただの水滴だ」と放置してしまうと、住まいとご家族の健康に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
結露を放置するとどうなる?知っておきたい3つのリスク
1. カビやダニによる健康被害
結露によって発生する湿気は、カビやダニにとって理想的な繁殖環境となります。
このカビの胞子を吸い込んでしまうと、アレルギー性鼻炎や喘息、アトピー性皮膚炎などを引き起こす可能性があり、すでに症状を抱えている方にとっては悪化の原因にもなりかねません。
特に小さな子どもや高齢者がいる家庭では、健康被害への注意が必要です。
2. 住宅の劣化と資産価値の低下
結露による水分が、窓枠の木材・壁紙・カーテンなどに染み込むことで、シミ・腐食・剥がれといった劣化が進行します。
このような状態を長期間放置してしまうと、壁の内部や床下にまでダメージが広がり、建物そのものの寿命を縮める要因となります。
また、こうした劣化は住宅の資産価値の低下にもつながるため、将来的に売却や貸し出しを考えている場合にも無視できないリスクです。
3. 断熱性の低下と光熱費の増加
そもそも窓は、住宅の中で最も熱の出入りが多い部分です。
結露が頻繁に発生しているということは、窓の断熱性能が十分でないサインでもあります。
外の冷気が室内に伝わることで、暖房の効きが悪くなり、その分だけ光熱費が余計にかかるという悪循環が起こりやすくなります。
つまり、結露を放置することで、快適性を損なうだけでなく、家計にも大きな影響を与えてしまうのです。
これらのリスクを避けるためにも、結露対策は非常に重要です。
【費用別】まずは試したい!手軽にできる窓の結露対策(DIY編)

本格的なリフォームを検討する前に、まずは自分でできる対策から始めてみたい、という方も多いでしょう。
幸いなことに、費用を抑えながら結露を軽減する方法はいくつか存在します。
ここでは、誰でも手軽に始められるDIYでの結露対策を「グッズを活用する方法」と「生活習慣を見直す方法」の2つのアプローチからご紹介します。
ご自身のライフスタイルや予算に合わせて、試しやすいものから取り入れてみてください。
100均グッズから始める対策|効果と「効かない」と言われる理由
ホームセンターや100円ショップでは、結露対策に役立つ便利なグッズが多数販売されています。
手軽に始められる一方で、それぞれの特性や限界を理解して使うことが大切です。
ここでは代表的なDIYグッズの効果と、注意点をまとめました。
手軽に始める窓の結露対策グッズ|効果と注意点を解説
- 吸水タイプ:結露吸水テープ(価格目安:110円~)
もっとも手軽に始められる対策として人気なのが、「結露吸水テープ」です。
100円ショップなどでも手に入りやすく、窓に貼るだけで発生した水滴を吸い取り、窓枠や床に垂れるのを防ぐ効果があります。貼り付けも簡単で、デザインも豊富なのでインテリアの雰囲気に合わせやすいのがメリットです。
ただし注意点としては、結露の発生自体を防ぐことはできない点、吸水量に限界があるため定期的な交換が必要な点があります。あくまで“応急処置”として使いたいグッズです。
- 断熱タイプ:結露防止シート(価格目安:500円~2,000円)
「結露を根本から抑えたい」と考える方におすすめなのが、「結露防止シート」。
ホームセンターや生活用品店などで販売されており、窓に貼ることで空気の層を作り、断熱性能を向上させて結露の発生を抑える仕組みです。適切に施工すれば、結露の発生を未然に防ぐ効果が期待できるほか、暖房効率の向上による省エネ効果も見込めます。
一方で、貼り付けにやや手間がかかることや、製品によって見た目に影響が出る場合がある点、効果に個体差があることには注意が必要です。
- コーティングタイプ:結露防止スプレー(価格目安:800円~2,000円)
もっと手軽に対策したいという方には、「結露防止スプレー」も選択肢のひとつです。
スプレータイプは、窓ガラスに直接吹きかけて膜を作ることで、水滴がつきにくくなる撥水・親水効果を得られます。透明なコーティングなので、窓の見た目を損なわずに使用できるのも大きなメリット。ただし、効果の持続期間が短め(数週間〜1ヶ月程度)で、定期的な塗り直しが必要な点には注意が必要です。
また、スプレー後に多少のにおいが残る製品もあるため、敏感な方は成分表示を確認しましょう。これらのグッズが「効果なし」と言われる主な理由は、結露の根本原因である「室内の湿度」と「窓の断熱性の低さ」を完全には解決できないためです。グッズはあくまで対症療法と捉え、次に紹介する生活習慣の改善と組み合わせることが重要になります。
換気・除湿・暖房器具の工夫で湿度をコントロール
結露の最大の原因である室内の湿気を、日々の生活習慣を見直すことでコントロールしましょう。
少しの工夫で、結露の発生を大幅に抑えることができます。
1. こまめな換気で空気を入れ替える
室内にこもった湿気を外に逃がす最も効果的な方法です。
1時間に5分から10分程度、2ヶ所以上の窓を開けて空気の通り道を作ると効率的です。
特に調理中や入浴後、洗濯物を部屋干ししている時などは、積極的に換気扇を回したり窓を開けたりしましょう。
2. 除湿機やサーキュレーターを活用する
換気だけでは追いつかない場合、除湿機で強制的に湿度を下げるのが有効です。
サーキュレーターを併用して室内の空気を循環させると、部屋の隅々まで効率よく除湿できます。
窓際にサーキュレーターを置いて空気を送るだけでも窓表面の温度が下がりにくくなり、結露防止に繋がります。
3. 水蒸気を発生させにくい暖房器具を選ぶ
暖房器具の中には、燃焼の際に水蒸気を発生させるタイプがあります。
結露対策の観点からは、水蒸気を発生させないエアコンやオイルヒーター、パネルヒーターなどがおすすめです。
石油ファンヒーターやガスファンヒーターを使用する場合は、特にこまめな換気を心がけてください。
暖房器具の種類別メリット・デメリットと結露への影響
エアコン
エアコンは、水蒸気を発生させない暖房器具の代表格です。
部屋全体を均一に暖めることができ、安全性も高いため、ファミリー層や高齢者のいる家庭にも適しています。
ただし、空気が乾燥しやすい点には注意が必要で、暖まるまでに時間がかかることがあるのもデメリットの一つです。
加湿器との併用で快適性がアップします。
オイルヒーター
こちらも水蒸気を出さない暖房器具で、空気を汚さずじんわりと室内を暖めてくれるのが特徴です。
乾燥しにくい暖房器具を探している方にぴったりで、音も静かなので寝室や子ども部屋にも向いています。
一方で、暖まるまでに時間がかかることや、電気代が比較的高くつく点はあらかじめ理解しておきたいところです。
石油・ガスファンヒーター
石油やガスを燃焼させて暖めるタイプのファンヒーターは、即暖性が高く、パワフルな暖房能力が魅力です。
寒い朝や短時間で暖めたいシーンには非常に便利ですが、燃焼時に大量の水蒸気を発生させるため、結露の原因になりやすいという大きなデメリットがあります。
さらに、使用には定期的な換気や燃料補給が必要になるため、日常的なメンテナンスの手間も考慮しておく必要があります。
【根本解決】プロに頼む本格リフォーム|内窓・ガラス交換で冬の悩みを解消

DIYでの対策を試しても効果が不十分だったり、毎年の結露対策にうんざりしていたりするならば、プロによる本格的なリフォームが最も確実な解決策となります。
窓のリフォームは、結露の問題を根本から解決するだけでなく、住まいの快適性を大きく向上させる様々なメリットをもたらします。
断熱性能が上がることで、冬の寒さや夏の厳しい暑さが和らぎ、一年を通して過ごしやすい室温を保ちやすくなります。
その結果、冷暖房の効率がアップし、長期的に見て光熱費の削減にも繋がるのです。
目的と費用で選ぶ|内窓・ガラス交換・サッシ交換を徹底比較
窓のリフォームには、主に「内窓(二重窓)の設置」「断熱ガラスへの交換」「サッシの交換」という3つの方法があります。
それぞれに特徴があり、効果や費用、工期が異なります。
ご自身の住まいの状況や予算、そして何を最も重視したいかに合わせて、最適な方法を選びましょう。
窓のリフォーム3つの方法|費用・効果・工期を比較して選ぶ
結露や断熱の悩みを根本から解決するには、窓まわりのリフォームが非常に効果的です。
ここでは、代表的な3つのリフォーム方法について、それぞれの効果や費用感、工期の目安をわかりやすくご紹介します。
- 内窓(二重窓)の設置
もっともバランスの取れたリフォーム方法として人気なのが、内窓(二重窓)の設置です。
既存の窓の内側にもう1枚窓を取り付けることで、断熱・防音・結露防止のすべてに高い効果を発揮します。
費用相場は1箇所あたり8万円~15万円程度で、工事自体は約半日で完了することが多いため、手軽に始めやすいのも魅力です。
- 断熱ガラスへの交換
比較的安価で済ませたい場合には、断熱性能のあるガラスへの交換という選択肢もあります。
既存のサッシをそのまま使えるため、費用を抑えつつ断熱・結露防止効果をある程度期待できるのが特徴です。
防音性はやや控えめですが、費用は1箇所あたり5万円〜12万円程度と手頃で、工期も1〜2時間程度と短時間で済みます。
- サッシごと交換するフルリフォーム
より本格的に性能を高めたい方には、サッシごと交換するリフォーム(カバー工法など)がおすすめです。
結露や断熱の問題を根本から改善でき、特にアルミサッシから樹脂サッシへ変更することで性能が大幅に向上します。
防音性もそこそこ高く、窓まわり全体の刷新によって住まいの快適性が大きく変わるのが最大のメリット。
ただし、費用は1箇所あたり15万円〜30万円以上と高めで、工期は半日から1日程度かかるケースが多いです。
※上記はあくまで参考価格です。実際の費用は、作業内容や部品代、出張エリアなどによって異なる場合があります。
【埼玉の住宅事情に特化】あなたの家に最適な結露対策の選び方

ここまでは一般的な結露対策について解説してきましたが、最適な方法は住んでいる家の種類によっても異なります。
例えば、気密性の高いマンションと、築年数の経った木造戸建てでは、注意すべき点や効果的な対策が変わってきます。
このセクションでは、埼玉県によく見られる住宅タイプを想定し、それぞれのケースに合わせた具体的な対策の選び方をご紹介します。
あなたの住まいに当てはめて、最適な解決策を見つけるための参考にしてください。
【住宅タイプ別】結露の特徴とおすすめの対策方法
住まいの種類によって、結露の発生しやすさや有効な対策は異なります。
ここでは、木造戸建て・分譲マンション・賃貸住宅の3タイプに分けて、結露の特徴と効果的な対策を解説します。
木造戸建て(特に築古住宅)
- 結露の特徴・注意点
築年数が経った木造住宅では、窓まわりだけでなく壁や床、押入れなど家全体で結露が発生しやすい傾向があります。 また、断熱材が不足していたり劣化していたりするケースも多く、断熱性・気密性ともに低いため、すきま風で窓が冷えやすいという課題も抱えています。
- おすすめの対策
もっとも効果的なのは、断熱性能の高い樹脂サッシへの交換です。 ただし費用がかかるため、予算を抑えたい場合は、家全体の断熱バランスを見ながら内窓を設置するのも有効な手段です。 また、壁内での結露(内部結露)のリスクもあるため、断熱リフォーム専門の業者に相談することをおすすめします。
分譲マンション
- 結露の特徴・注意点
分譲マンションは気密性が高い反面、湿気がこもりやすいのが特徴です。 コンクリート造のため、壁面自体が冷えやすく、窓だけでなく壁にも結露が発生することがあります。 また、窓の交換は共用部分に該当する場合が多く、管理規約で制限されている点にも注意が必要です。
- おすすめの対策
まずは、管理規約の範囲内で可能な「内窓の設置」を検討しましょう。 また、24時間換気システムを正しく使い、湿気をため込まないよう空気の流れを意識することが重要です。 家具を壁から少し離して配置するなど、空気の通り道を作る工夫も効果的です。
賃貸住宅
- 結露の特徴・注意点
賃貸住宅では、リフォームやDIYに制限があるケースがほとんどです。 また、建物構造的に結露が発生しやすい物件も存在します。 さらに、退去時の原状回復義務を考慮する必要があるため、施工には注意が必要です。
- おすすめの対策
基本的には、工事不要の結露対策(吸水テープ、除湿機など)が現実的です。 最近では、傷をつけずに設置・撤去できる簡易的な内窓も市販されているため、そうした製品を活用するのも一つの方法です。 結露がひどく、生活に支障をきたす場合は、まずは管理会社に相談するようにしましょう。
ご自身の住まいのタイプに関わらず、対策を始める前には、特にマンションやUR賃貸の場合は管理規約などを必ず確認するようにしましょう。
失敗しない!埼玉県で信頼できるリフォーム業者選びの5つのポイント

結露対策のリフォームは、決して安い買い物ではありません。
だからこそ、技術力があり、信頼できる業者に依頼することが何よりも重要です。
埼玉県内にも多くのリフォーム業者がいますが、どこに頼めば良いか迷ってしまう方も多いでしょう。
ここでは、後悔しない業者選びのための5つのチェックポイントをご紹介します。
後悔しないために!結露対策・窓リフォーム業者を選ぶ5つのチェックポイント
結露対策や窓のリフォームは、決して安くない投資です。だからこそ、信頼できる業者選びがとても重要です。
以下の5つのチェックポイントを押さえておくことで、トラブルのないリフォームを実現できます。
1. 地元での施工実績が豊富かどうか
まず確認したいのは、その業者が自分の住んでいる地域で豊富な施工実績を持っているかどうかです。
公式サイトなどで、埼玉県内や、できればお住まいの市区町村での施工事例が掲載されているかをチェックしましょう。
また、結露や断熱に関する専門的な知識を持っているかどうかも重要なポイントです。地域の気候や建物の傾向に詳しい業者なら、より的確な提案が期待できます。
2. 見積もりの内訳が明確か
「工事一式」などのざっくりした見積もりではなく、商品代・工事費・諸経費などが細かく明記された見積書を出してくれる業者を選びましょう。
複数の業者から相見積もりを取り、内容と金額をしっかり比較検討することが、適正価格での契約につながります。
不明な点があれば、遠慮せず質問し、納得できる説明をしてくれるかどうかも判断基準の一つです。
3. 補助金制度についての知識と申請サポートがあるか
近年のリフォームでは、国や自治体の補助金制度の活用が不可欠です。
たとえば「先進的窓リノベ事業」など、活用できる制度に精通していて、申請代行や書類のサポートがしっかり整っている業者かどうかを確認しましょう。
制度をよく理解している業者であれば、「この条件ならこの補助金が使えますよ」と積極的に提案してくれるはずです。
4. 保証内容やアフターサービスは充実しているか
工事が終わったあとに、不具合やトラブルが発生するケースもゼロではありません。
そのため、メーカー保証とは別に、工事自体に対する独自の保証(工事保証)があるかを確認しましょう。
また、施工後に何か問題が起きた際、迅速に対応してくれるアフターサービス体制が整っているかも大切なチェックポイントです。
5. 担当者の対応が誠実で丁寧か
最後に、実際にやりとりをする担当者の人柄や対応力も非常に重要です。
こちらの悩みや希望を親身に聞いてくれたり、専門用語を使わずに分かりやすく説明してくれたりするかをチェックしましょう。
また、メリットだけでなくデメリットも正直に伝えてくれる姿勢や、強引な営業をしない誠実さがあるかどうかも、信頼できるかどうかの判断材料になります。
これらのポイントを踏まえ、複数の業者と実際に話をしてみて、総合的に信頼できると感じたパートナーを選ぶことが成功の鍵です。
【Q&A】結露対策でよくある疑問に回答!

Q1. 窓をリフォームしたら、本当に結露は完全になくなりますか?
A. 完全に「ゼロ」にはならないケースもありますが、大幅に減少するのが一般的です。特に内窓や樹脂サッシの導入によって、発生頻度や水滴の量が激減したという声が多く寄せられています。
Q2. 結露対策とカビ対策はどう違うの?
A. 結露対策は「カビの原因を断つ」ことに直結しています。湿気をため込まない住環境づくりが、結果としてカビやダニの発生を抑え、清潔で健康的な室内環境を保つことにつながります。
Q3. マンションだと内窓しかできないの?
A. 原則として「窓の外側(サッシなど)」は共用部に該当するため、勝手な工事はNGです。ですが、「内窓」は専有部に設置できるため、多くの管理組合でも問題なく許可されています。
知らなきゃ損!結露対策に関する“よくある誤解”

結露対策に関しては、インターネットや口コミなどで広がった誤解や思い込みが意外と多く存在します。
間違った対策では、十分な効果が得られないどころか、かえって住まいを劣化させてしまうことも。
ここでは、代表的な誤解とその実際のところをわかりやすく解説します。
■ 誤解1:「結露テープを貼ればもう安心!」
よくあるのが、「結露対策=吸水テープを貼ること」と思い込んでしまうケースです。
たしかに吸水テープは、発生した水滴を吸い取る応急処置としては有効ですが、結露自体を防ぐ効果はありません。
根本的な結露対策をするには、窓まわりの断熱性を高めることが不可欠です。
つまり、吸水テープはあくまで“その場しのぎ”であり、本質的な解決には断熱リフォームや内窓の設置などが必要になります。
■ 誤解2:「結露って冬だけ注意すればいいんでしょ?」
結露は「冬の悩み」と思われがちですが、実は夏や梅雨時期にも発生することがあります。
とくに冷房を効かせた室内で、外気との温度差が大きい場合に起きる「逆結露」がその代表です。
たとえば、外が蒸し暑く、室内が冷えた状態になると、窓の外側や壁面が結露することもあります。
このように、結露は季節を問わず湿度と温度差があれば発生する現象なので、年間を通した湿度管理が重要になります。
■ 誤解3:「古い家は風通しがいいから結露しない」
「昔ながらの木造住宅は通気性があるから結露しにくい」と思われることもありますが、これは半分正解・半分誤解です。
実際には、古い木造住宅こそ、断熱材が不十分だったり劣化していたりすることが多く、外気の影響を受けやすい構造になっています。
また、気密性が低く、すきま風で窓まわりが極端に冷え込むため、結露が起きやすい条件がそろっている場合も。
「古い=結露しにくい」とは限らず、むしろ築年数の古い住宅ほど断熱性を見直す必要があるのです。
【未来予測】気候変動と結露の“これから”
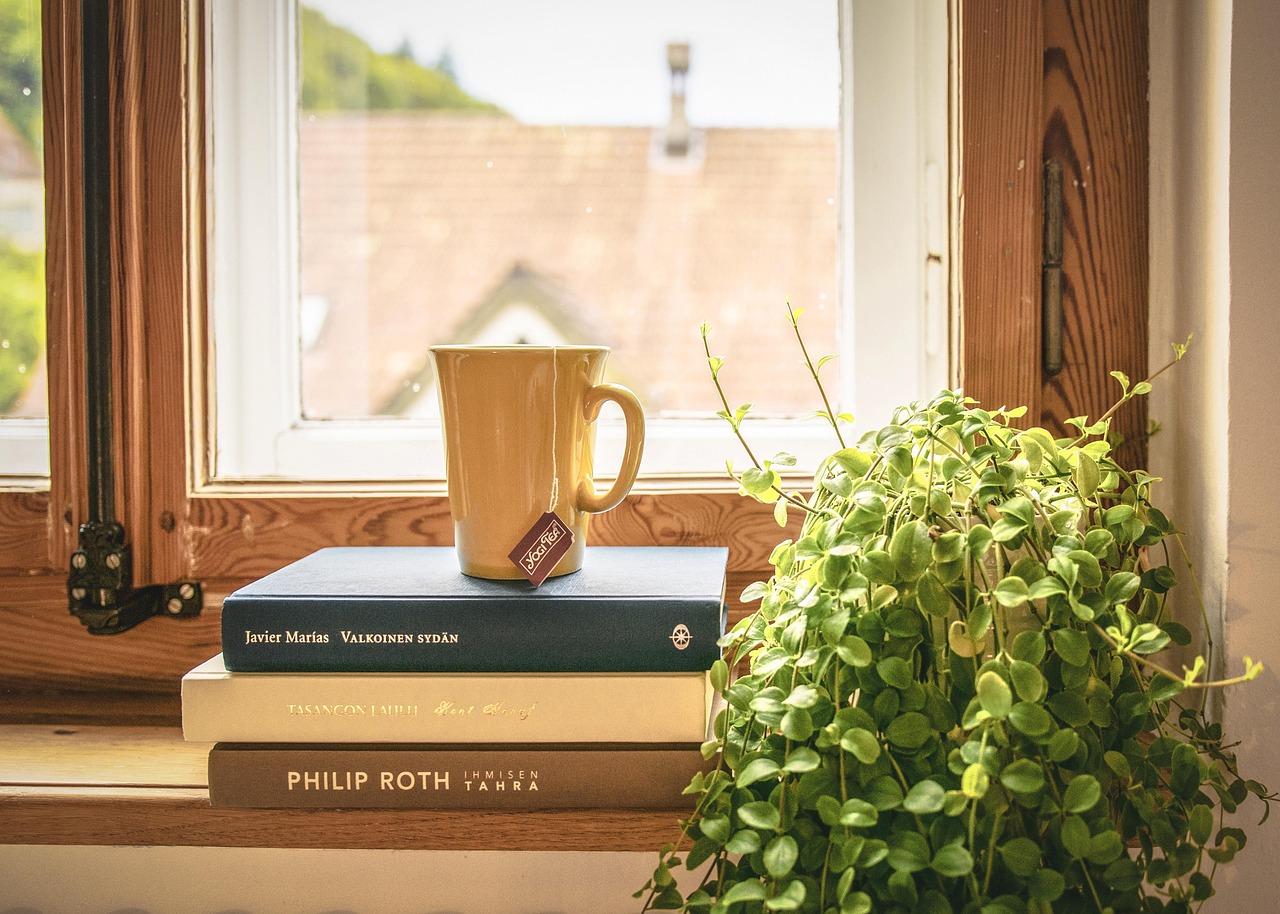
地球温暖化によって、日本の冬は「寒暖差の大きい不安定な気候」へと変化しつつあります。埼玉県でも、晴天と寒波が交互に来る日が増加傾向にあり、窓の冷え込み→結露の発生が加速しています。
また、住宅の高気密化も進み、「換気しにくい」構造の住まいが増えているため、“結露しやすい家”が増えていくとも言えます。
今からの断熱・換気対策は、未来の快適性への先行投資とも言えるでしょう。

)